[Aohitokun's Thoughts]「アートワールド」byアーサー・ダントーを巡って
![[Aohitokun's Thoughts]「アートワールド」byアーサー・ダントーを巡って](https://www.japan-live-exhibits.com/wp-content/uploads/2020/10/1006-01.jpg)
Tokyo Live Exhibitsも徐々にアクセスを増やしてきました。
みなさま、どうもありがとうございます!
過去、アクセスの多かった自分のブログを書き直して再掲します。
これはインディペンデント・キューレター辻憲行氏が2013年に開催した、コロンビア大哲学教授であり美術評論家アーサー・ダントー(1924年米国生まれ)の「アートワールド」(1964年刊)読書会に参加した際、自分なりの考えを書いたものになります。参考サイト:芸術係数blog:http://gjks.org/(今はサイトにアクセスできません)
この「アートワールド」とは、ダントーが、現代アートとは何か?ということをパラダイム論的に提唱した芸術論です。
そのパラダイム論とは、バラバラに点在していると思われる事象を、ひとつの枠組み(パラダイム=価値基準)で囲って考えてみる。それに対する反論はべつの枠組みを作って比較するという思考方法だそうです。
さて、ヨーロッパでは、芸術に対する見方とは、まずギリシャ時代の哲学者プラトンは、芸術はモノをそっくりに真似て描く技術であり、それによって制作された作品を芸術とする模倣論から始まったといいます。
プラトンは、何で人間は何も知識がなく生まれてくるのに物事や言葉をあっという間に習得し、理解するのか?と考えた。
まずイデアという本物の世界があって人は忘れていたにすぎず、生きていくうちにそれらを思い出す。
そして芸術とは、イデアを得た人間が、作り出したモノを模倣したにすぎない、とプラトンは捉えました(想起説・イデア論)。
ところが科学技術や思想哲学の進歩があり、ルネサンスやフランス革命、産業革命による個人の意味とその確立、自由と平等、写真の発明などで芸術の存在意味も変わってきました。
たとえば印象派絵画のようにそれまでは、物事を映す鏡にすぎなかった芸術が、アーティスト個人が捉える、見えるような世界を描くことに変わった。
そこに芸術の価値があり、存在意義が生じた。
なぜならヨーロッパ文明の考え方では、人間個人に一番価値があり、それが世界の基準になり、発展進化することも一番大事だと思われている(これに関しては、宗教がすごく影響していると思う。自分は、別のブログでこのことに関しては書いています。折があったら再掲します)。
と同時に、それら自分の行動、思考を言動で訴えていくこと(価値の共有)も義務に近いのです。でないと、あなたは存在していない、と見なされる。
ある意味、当たり前のことのように聞こえますが、日本に育った私たちには、そういう言語による裏付け作業や、個人の意味を、つきつめて考えるような社会に育っているのでしょうか?

これも以前、ブログにも書いたと思いますが、欧米語と日本語の文法構造を見てもよくわかると思います。
ほとんどの欧米語はSVO文法です。好きだよ、では通じない。私は!あなたが!好きです!と主語、述語、目的語などが揃っていないとなかなか通じません。
裏を返すと常に「私」が、中心にいる行動する世界観ではないでしょうか。
話が飛びましたが、ダントーはプラトンの言う芸術観を、「芸術は模倣である」というパラダイムでくくる。
次に「芸術は表現である」というパラダイムでくくった。
で、それらを併記して、現代アートの可能性、アートか否かを探ってみる。
たとえば、
芸術は模倣であって、表現である。=フォービズム、印象派など
芸術は模倣でなく、表現である。=抽象画など
芸術は模倣であって、表現でない。=スーパーリアリズム、古典絵画など
芸術は模倣でなく、表現でない。=コンセプチュアルアート、リレーショナル・アートなど
といった具合です。
では、これからはどんな可能性があるのか?と問うたとき、ダントーはワンフレーズ、そこに増やすことを言った。
つまり、
芸術は模倣である。
芸術は表現である。
芸術は○○である。
ダントーは、そうやっていくことで、新たに芸術が生まれる、と。
そして、〇〇に当てはまるのが、アートワールド だった。

しかしアーティストを目ざす人種にとっては、あまりよくない。つまり評論家がアートの価値をきめることとなり、ダントーの付け足すワンフレーズいかんで、芸術か否かにもなるというのです。いわばアーティスト不要論にも通じてしまう。
たとえば現代だったら、
芸術は、AIである。
と言われたアーティストは一瞬にして消えてしまう。
しかし前にも述べたが、これはあくまでも人間中心主義の欧米的思考回路です。
そのうえ、芸術は新しい切り口、パラダイムを表示することだから、ダントーの芸術観にワンフレーズを加えてみても、それは結局、模倣論になってしまう。
ダントーの述べた、芸術論は、それのみしか芸術的価値はないと自分は思います。
また、先も述べたように、日本には違った世界観があります。森羅万象、神が宿り、人も青人草から生まれています(古事記より)
それは自然中心主義なのか、刹那論なのかはわかりません。
なんとかなるさ、これでいいのだ、仕方ない、男は黙ってなんとかビール。
芸術は模倣である。
芸術は表現である。
芸術は日本である。
というように、なんか言葉を感覚的にとらえることができるのが、素晴らしいと思います。
と言うより、世界はどんどん感覚的(直感的)になっているような気がしてなりません。
だ・か・ら、アートだぁ~
ちょっとオチが苦しかったかぁ。
(写真は、青人君のブループリントによる)
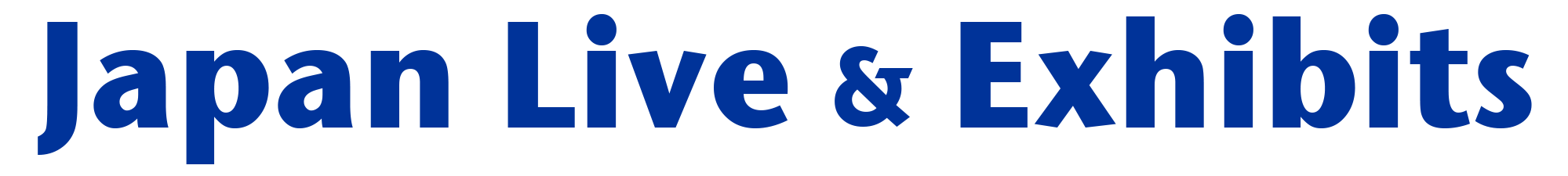
![[Aohitokun's Thoughts]サイトオープン!豪華執筆陣でブログも充実!](https://www.japan-live-exhibits.com/wp-content/uploads/2020/09/Kyub3-140x96.jpg)
![[The Evangelist of Contemporary Art]ヨコハマトリエンナーレ2020とは何だったのか?(その1)](https://www.japan-live-exhibits.com/wp-content/uploads/2020/10/venezia02-2-140x96.jpg)
Comments